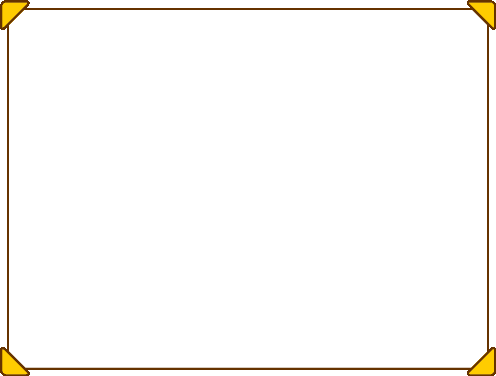午前の学科は、私にとって予想以上に厳しい問題が多かったです。最初の何問かは全くわかりませんでした。一問として自信がない状況の中、あっという間に30分たってしまい、慌てて点字についての設問がある後ろからやり始めました。福祉や視覚障害についての問題は「ハンドブック」に載っていない事柄が多かったように感じました。しかも、あがっているせいか、点字で読む文章は墨字のようになかなかはっきりと頭に入ってこないのです。
後で見直すと、見事に言葉のあやにひっかかったりしていました。内容も隣で受けている視覚障害者の方にはきっと常識なんだろうな?と思うようなものが多々ありました。自分の視野の狭さを突きつけられた気がして、愕然としながら終えました。
逆に午後は、午前がきつかっただけに易しく感じました。時間も足りましたし、文章の内容も平易だったように思いました。こちらは普段やっていることを、そのままやればよいことなので、経験豊富な点訳者の方なら、苦労はないと感じました。
さて、今回、奇跡的!に合格通知をいただくことができました。実は、学科があまりにもできなかったので、通知を見ても、「目の錯覚か?」と、家族にも確認してもらうほどでした。
これを書いている今も、「合格は手違いでした」と訂正がくるのでは?と心配な気持ちがあるくらいです。1月に証明書が届くそうですが、実際に届いたあかつきには、点字技能師の先輩方の足を引っ張らないように、自分なりに勉強を続けていきたいと思います。
今まで、点字を通して知り合った多くの方に、心から感謝しています。
平成17年1月 日点協通信第22号より(NPO法人 日本点字技能協会発行)
後で見直すと、見事に言葉のあやにひっかかったりしていました。内容も隣で受けている視覚障害者の方にはきっと常識なんだろうな?と思うようなものが多々ありました。自分の視野の狭さを突きつけられた気がして、愕然としながら終えました。
逆に午後は、午前がきつかっただけに易しく感じました。時間も足りましたし、文章の内容も平易だったように思いました。こちらは普段やっていることを、そのままやればよいことなので、経験豊富な点訳者の方なら、苦労はないと感じました。
さて、今回、奇跡的!に合格通知をいただくことができました。実は、学科があまりにもできなかったので、通知を見ても、「目の錯覚か?」と、家族にも確認してもらうほどでした。
これを書いている今も、「合格は手違いでした」と訂正がくるのでは?と心配な気持ちがあるくらいです。1月に証明書が届くそうですが、実際に届いたあかつきには、点字技能師の先輩方の足を引っ張らないように、自分なりに勉強を続けていきたいと思います。
今まで、点字を通して知り合った多くの方に、心から感謝しています。
平成17年1月 日点協通信第22号より(NPO法人 日本点字技能協会発行)